
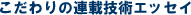
| 第14回 携帯電話(その2) | 2003年8月29日 |
平成15年6月末で77,213,900の加入者数になった携帯電話ですが、ご承知の通り、日本には4社の携帯電話会社(これをキャリアと呼びます)がシェア争いを展開しています。最大手がDoCoMo、次がAU、そして今や英国系の会社であるJ-Phone、最後がTu-Kaです。平成15年6月末の契約数はDoCoMoが44,361,000(57.5%)、AUが14,673,500(19%)、J-Phoneが14,439,800(18.7%)、Tu-Kaが3,739,600(4.8%)で、Tu-Kaのみが減少となっているのが目立ちます。
この最下位のツーカー、『突然ですが、ケータイで動画が見られるって、そんなにうれしいことですか?』から始まるユニークな広告を思い出します。この広告、携帯電話の基本を大切にすべきという主張ですが、携帯電話に動画機能を追加できなかった同社の現実を認めているような気がしてちょっと悲しくなります。
筆者も電話機は電話がちゃんとできるのが基本という考えがあります。最近の携帯電話に搭載されているいろいろな機能が欲しいとは思わない一人です。メール機能もいらない。カメラもいらない。動画なんて・・・。ですが、新しい機種を買うと付いてくるのも現実です。キャリアとしては通信量を増やして収益にしたいと考えているのでしょうが、はたしてそれを使いこなしているユーザーがどのくらいいるのでしょうか。DoCoMoのiアプリという機能があります。携帯電話で使うソフトウェアをダウンロードして実行させるものですが、期待ほど使われていないという話を聞いたことがあります。これはJAVAという言語で書かれたソフトウェアですが、搭載されているCPUに依存しない特徴がある反面、実行速度がどうしても遅くなるという欠点があります。増収を期待するキャリア、同業他社と差別化を図る携帯電話メーカーの思惑がこのような多機能化を進めたのでしょうが果たしてユーザーが使いこなしているのか、ちょっと疑問を感じます。
携帯電話が始めて出現した頃、通話料も非常に高く、また、電話機も大きく重かったのを覚えています。それが、ワイシャツの胸のポケットに入る位になり、重量も100g前後、リチウム電池のおかげで長時間の待ちうけも可能になった。これは脅威的な進歩です。携帯電話がアナログの頃、米モトローラ社のマイクロタックという電話機を見たときの驚き、それが日本メーカーの努力で大幅に小型軽量化された。その携帯電話にインターネット閲覧機能が追加され、メールの送受信が可能になった。加えて小さなディジタルカメラが組み込まれた。そして、それらの普及が新しい価値観を生むと同時に問題も起こしています。まず、メールの使われ方、本来、電子メールは電話と異なり実時間で反応するものではありませんでした。自分の都合が良い時間にアクセスする。そして、返事を書く。せいぜい一日一回で十分であろうと考えていましたし、そのメリットは通信コストの安さにあると思っていました。しかし、昨今の携帯メールでは相手が送ると同時に受信、すぐに返事の入力をしています。キーボードを押す速さに驚かされます。携帯電話のディジタルカメラ、肖像権の侵害、また、本屋などで立ち読みし、必要な部分だけを撮影するというような使われ方もしているようで、著作権の侵害といった問題も起こしています。このような現象を新しい価値観と考えるべきなのでしょうか。
携帯電話一台に支払う費用の平均を5,000円と仮定すると、その市場規模は3,800億円となります。この費用、限られた収入から携帯電話会社に支払われる(最優先?)ますが、携帯電話の普及で影響を受けたビジネスがかなりあるようです。
筆者にとって携帯電話は電話機、確実に通話できるのが基本と考えます。そして、電話機としてしか使いません。よって、余分な機能はいらない。信頼性の向上、そして、壊れないこと。基本に忠実であって欲しいと望んでいます。
| << BACK | NEXT >> |
