
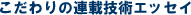
| 第13回 携帯電話(その1) | 2003年8月29日 |
現在、携帯電話の加入者数は平成15年6月末で77,213,900になっています。平成15年3月末時点の日本の人口が12,741万人ですから過半数の人々が携帯電話を持っている計算になります。さて、加入者電話の数は、これは携帯電話の普及で固定電話と呼ばれますが、統計によると平成13年度末で50,740,000契約ですから、間違いなく携帯電話の方が多くなっています。
最初にこの普及が著しい携帯電話についてちょっと知識を。この携帯電話英語ではCell Phoneです。このCellとは一つの基地局がカバーするエリアを意味し、複数の基地局で広い範囲で通信できるようにしているのでこのように呼ばれています。日本ではPDC方式と呼ばれる日本独自の方式でディジタル化が完了しています。一部CDMA方式も使われていますが、日本以外でPDCを採用している国がないので日本の携帯電話を海外に持ち出して使うことはできません。米国には米国独自の方式があり、欧州、東南アジア、オセアニアでは欧州で開発されたGSM方式が使われています。世界規模で考えると、欧州の規格であるGSM方式を採用している地域が最も広いのですが、日本でこの方式は使われていないので海外で携帯電話を使うにはその地域で使われている方式の電話機が必要になります。最近では海外旅行に行く人向けに海外用の携帯電話を貸し出すサービスもあります。
有線式の固定電話では各国に規格があるものの、類似しており、共通の電話機が使えたのですが、携帯電話は全く違うのです。さて、この携帯電話、常に基地局と通信しています。電話会社ではその携帯電話がどの基地局のエリアにいるのかどうかを常に把握しておかないとそこに電話をかけることができません。車や列車では移動するので基地局を切り替えて通信を行います。よって、非常におおまかですが、携帯電話が存在した地域は電話局で把握されているのです。基地局と携帯電話の通信は数分ごとに短い時間行われますが、電波が弱くなるとこの間隔が短くなります。電波が弱くなるということはそれまで通信してきた基地から遠ざかっていることで、別の基地局を探さなくてはならないからです。また、地下街やビルの中など電波が届かない場所、すなわち、圏外ではこの間隔がさらに短くなり頻繁に基地局探しをするようになります。結果、圏外にいると基地局を探す送信頻度が高くなるので早く電池を消費してしまいます。圏外にいるときには電源を切っておく方が電池を長持ちさせられます。
従来の固定電話は電話局に設置された交換機に接続されています。よって、交換機の収容能力を超えた電話機は接続できません。しかし、携帯電話の場合にはこのような制約はなく、通信能力を超えた数の電話機が存在できます。実際に加入者全員が同時に電話をかけることは考えられません。しかし、物理的に利用できる周波数帯域が有限なので、一つの基地局で同時に通話できる携帯電話の数は限られます。多くの人々が集まる繁華街で特定の時間に通話ができなくなるのはこれが原因になっています。便利な携帯電話ですが、いつも通話できるとは限りません。全ての回線が使用中の場合、すぐに話中音が聞こえます。どうしても連絡したい場合には繰り返しダイアルして回線を確保するしか方法がありません。
かなり以前ですが、基地局が把握できる電話の数が限られている電話会社がありました。使用頻度が低い、すなわち、ずっと待ち受け状態が続くとその電話機がエリア内にないことになってしまうのです。よって、誰からも電話がかけられない状態になってしまいました。これを回避するには時折電源を切り、再び基地局に登録しなければなりませんでした。現在、このような現象は起こらなくなっています。
| << BACK | NEXT >> |
