
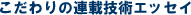
| 第12回 加入者電話 | 2003年8月29日 |
これまで電話は加入者電話だけでしたが、携帯電話が普及したため、固定電話と呼ばれるようになっています。NTT東日本とNTT西日本で日本全体をカバーし、他に固定電話を提供する電話会社はありません。電話局に交換機を設置し、それぞれの加入者に専用の銅線で接続しています。この固定電話、電話が出現した明治時代と基本的に同じです。電話回線には電話局に設置された電池から直流48Vが供給され、基本的に電話機はこれを電源として動作するようになっています。NTTが日本電信電話公社と呼ばれていた時代、標準的に供給されていた電話機が俗に黒電話と呼ばれていたもので、600型電話機でした。回転式のダイアルで、コイルとコンデンサ、そして、カーボンマイクとマグネチックスピーカーが入っていました。トランジスタやICなどは入っていません。プッシュホンになってからトランジスタが入っていましたが、電源は電話局からの供給になっていました。
基本的に電話は通信の保証をすべきものと思われていました。緊急時に使用するものと考えられていたためで、停電になっても大丈夫なように電話局には蓄電池が使われていました。電話機が自由化され、電気店で販売されるようになった時も、その基本は電話局からの電力で動作するものが普通でした。しかし、電話機の機能が増加し、その消費電力が大きくなった頃から電話機が商用電源で動作するようになりました。それでも電話機としての基本機能だけは電話局からの電力だけで実現できるものがほとんどであったと記憶しています。その後、コードレスが普及してからは停電になると使えない電話機が増加しています。停電が起こることはめったにないので実質的な問題はありません。
ところが、災害の発生時に大規模な停電が起こります。実際、神戸で発生した阪神大震災では停電となったために電話がつながらなくなり、これが原因で混乱が起こったと聞いています。電話会社は通信の確保のために早急に復旧したのですが、電力が供給されなかったために通話ができない。そのために知人の安否がなかなかとれなかった。
電話回線の数は設置されている交換機の収容能力で決まります。そして、それらの電話機が全て同時に使われることがないと想定して約30%の電話機が使用されると想定した電源供給能力を用意しています。地震などの災害が発生すると多くの人々が電話をかけるために、電源の供給能力を上回る可能性があり、通信の確保ができない事態が発生します。現在ではこれを防ぐために災害が発生した場所にかかる電話の受信制限を行って通信を確保しているようです。
電話網は緊急時に使われることを想定し、通信の確保を最優先に考えています。実際、電話機に接続されている電線が電話局まで繋がっている。この確実性は他の方法では実現できないものです。日本の場合、電話が国営だった時間が長かったせいか現在もこの加入者線はNTTが保有しています。通信の自由化によりいくつか電話会社が生まれましたが、その事業は市外通話のみで、加入者線はNTTから借用しなくてはならないのです。これをラスト1マイルと呼んでこれらの電話会社が喉から手が出るほどほしいものです。インターネット接続が電話モデムからISDN、そして、ADSLに変わりつつあります。このいずれの方法もNTTが保有する加入者線を必要としているものです。
個人が携帯電話を持つようになり、固定電話があまり使われなくなったような気がします。かかってくるのも商品の売り込みや勧誘など、電話の使い方も変わってきたものだと実感します。しかし、この加入者線を利用する種種のサービスが普及してくると、NTTの収益も増える構図は明白でちょっと抵抗してみたくなるのは筆者だけではないと思います。
| << BACK | NEXT >> |
