
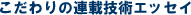
| 第20回 地上波ディジタル | 2004年3月1日 |
2003年12月1日から東京、名古屋、大阪地区で放送が始まったのが地上波ディジタル放送です。東京地区でこれを受信できるのは限られた地域ですが、総務省では順次サービスエリアを拡大していくと発表しています。地上波ディジタルとは現在のテレビ放送をディジタルにしてしまうもので、世界的には米国、英国が先行しています。そして、地上波という単語が耳新しいのですが、衛星放送と区別するために使われます。
日本で採用された方式はISDB-Tと呼ばれる独自のもので米国のATSC方式、英国のDVB-T方式とは全く互換性がありません。変調としてCOFDM方式が採用されています。これはDVB-Tと同じですが、6MHz(英国では7MHz)の帯域を13分割したセグメント方式となっています。また、日本と米国の方式にはHDTV(ハイビジョン)の規格があり、高精彩な画像もサポートされています。
英国ではすでにテレビ放送はUHF帯域になっていますが、米国と日本ではまだVHF帯域が使われています。テレビ放送を全てUHF帯域に移し、VHFを有効に使いたいというのが先進各国の考え方のようです。しかし、この帯域を何に使うのか具体的な案がまだないのが現実。日本では昨年10月からディジタル音楽放送(DAB)の試験放送が行われていますが、まだ受信機が市販されていません。
日本のディジタル放送は可能な限り統一された規格にするようになっています。まず、先行したBSディジタル放送と今回始まった地上波ディジタルは変調方式だけが異なり、BSディジタルと地上波ディジタルの共用受信機の実現が容易です。また、前述のディジタル音楽放送は車載ラジオの置き換えを狙ったもので、地上波ディジタルの13セグメントのうち一つだけを使います。このような受信機を1セグメント受信機と呼びます。携帯電話でテレビが見られるようになるとの発表がありましたが、これらは1セグメント受信機を想定しています。しかし、現時点でこの1セグメントのテレビ放送が行われるかどうかは決まっていません。この地上波ディジタルに採用されている方式は移動体受信で優れた性能が得られるとされています。走行中の車の中でも安定した映像が受像ができると言われています。時速80〜100kmなら安定な受信ができるとの実験報告もあります。しかし、現時点でこのような移動体向けの放送を行うと決めた放送局はありません。
地上波ディジタルは基本的にこれまでの放送を放送するサイマルキャストです。データ放送が追加されていますが、映像(番組)の内容は全く同じです。某国営放送局がハイビジョン放送を推進していますが、民間放送局では標準解像度の映像をハイビジョンに変換するアップコンバートで放送している時間が多いのも現実です。
東京地区のサービスエリアが非常に狭いのはアナログ・アナログ変換作業が進んでいないことが原因です。ディジタル放送のために放送各局に新たなチャンネルを割り当てなくてはなりませんが、残念ながらそれだけの空きチャンネルがない。そこで、すでにアナログ用に割り当てられたチャンネルを変更してディジタル用のチャンネルの確保をしなくてはなりません。すでにアナログで放送している信号を新たなディジタル放送で妨害することができないためです。東京タワーからディジタル放送の出力を増やすと受信障害が出る地域がまだ残っています。このアナ・アナ変換作業が進むにつれて地上波ディジタルのサービスエリアが拡大するはずです。
この地上波ディジタルを略して地デジと呼んでいるようですが、筆者だけでしょうか。なんか響きが悪い感じを受けるのですが。さて、この衛星と地上波のディジタルテレビ放送、今年の4月から民放も含め全てスクランブル放送になります。見るための費用はかかりませんがB-CASカードと呼ばれるICカードを登録する必要があります。
| << BACK | NEXT >> |
