
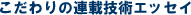
| 第18回 DVDの話 | 2004年1月8日 |
DVDプレーヤやDVDレコーダが売れているそうです。このDVD、数年前に出現した期待の商品であったが、なかなか普及しなかった経緯があります。DVDはDigital Versatile Discの頭文字をとったもので、日本語に直すとディジタル多用途(または万能)ディスクとなりますが、ディジタルビデオディスクと勘違いしている人も多いのではないでしょうか。
さて、このDVD、ディスクにはいくつかの種類があります。最も広く使われているのがDVD-Video、次にDVD-ROMとなります。ほとんど普及していませんがDVD-Audioの規格もあります。書き込みが可能なものには、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWがあります。ここまで6種類のDVDディスクの名前を書きましたが、これらの中のDVD-RAMとDVD-RWは他の3種類とフォーマットが異なるため互換性がありません。これらの規格は全てDVDフォーラムの規格ですが、これ以外の規格となっているのがDVD+RとDVD+RWです。これらの規格は独自規格でDVDフォーラムが既定しているものではありません。
DVDが出現する前には容量が650MBのCDがありました。これはディスクレコードの置き換えに開発されたもので、あっという間にそれまでの30cmLPを駆逐し、音楽配布の主流になりました。CDの出現から少しして出現したのがCD-ROM、これはデータの配布用でしたがこの普及にはフロッピーディスク並みのコストになるのを待つしかありませんでした。今考えると650MBは小さいように感じますが、日本語の一文字の表現に必要なのが2バイト(16ビット)ですから3億文字以上の情報をCD-ROM一枚に格納できると考えるとすごいものです。ポイントは器の価格よりも中身の価格になります。CD-ROMの製造コストが安くなり、大容量のデータを配布する必要が生じるまでCD-ROMは普及しなかった。雑誌の付録に使えるようになるまでは。
このように4.7GB(4700MB)ものデータが入るDVDの使い道はと考えると、どうしても映像になり、映画になります。事実、DVDは一本の映画を12cmのディスクに収める目的で開発されています。見たところCDと同じように見えますが、ずっと細かな工作精度が要求されるものです。これまで作られた映画の殆どが90分以内と聞いたことがあります。4.7GBで90分となると、毎秒約7Mビットになります。現在主流となっている映像の圧縮にMPEG-2が使われ、この圧縮率が1/30〜1/50とされているので、オリジナルの映像としては、210〜350Mビット毎秒のものになります。皆さんが毎日見ているテレビ放送、これを単純にディジタルにすると、約250Mビット毎秒です。これからもおわかりになるように、DVDで見られる映像は現在のテレビ放送レベルの映像(SDTV)であり、ハイビジョン映像(HDTV)の記録はできません。
3年前に始まったBSディジタル、そして、昨年末から始まった地上波ディジタルではハイビジョン映像が売りになっています。これを記録しようとすると、少なくともDVDの6倍以上の容量と読み出し速度が要求されます。すでに始まっている大容量の光ディスク、ブルーレイディスクは約400nmの波長の青色レーザーダイオードで読み書きするもので、これまでに50GBという非常に大きな容量のディスクを実現します。ちなみに、CDでは780nm、DVDでは650nmの波長のレーザーが使われていました。400nmは人間の目に見える最も短い波長、青、もしくは紫色の光です。ちなみに人間の目に見える最も長い波長は700nmと言われ、色は赤です。
ハイビジョン映像を手軽に記録できるようになるにはもう少し待たなくてはなりません。また、記録可能なDVDも2時間程度の記録にした方が良いようです。これ以上の長時間記録では実用にならないと聞いています。
| << BACK | NEXT >> |
