
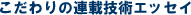
| 第6回 自律航法って何だ?(その2) | 2003年6月12日 |
現在、カーナビゲーションシステムの主流はハイブリッド航法、GPSと自律(自立)航法の組み合わせになっています。 開発当初、信頼性の高い自律航法システムを低価格で実現するのがとても困難でした。 前回お話した磁気センサ(正式にはフラックスゲートと呼ばれます)を使って何とか方位の特定ができないかを散々試したものでした。 しかし、このセンサは車体着磁の影響が大きく、その補正が事実上困難なため断念しました。 また、レートジャイロスコープと呼ばれるセンサも多くのメーカーで開発され、検討されました。 当時の磁気センサ(Tokin製)とレートジャイロ(村田製作所製)の写真を紹介します。 いずれも現在のカーナビゲーションシステムには使われていません。

レートジャイロスコープとは高速で動いている物体に外力が加わった時、 それまでの動きを保とうとするコリオリ力と呼ばれるひずみを電気的に検出して物体に加わった回転量を検出するものです。 すなわち、地磁気を検出する磁気センサのように絶対的な方位はわかりませんが、相対的、すなわち最初の向きがわかっていれば、 カーブを曲がった時の回転量から向きの変化を知ることができるわけです。 写真のセンサは特殊な金属で作られた三角柱を高速で振動させ、外力が加わった場合にその三角柱がねじれるのを圧電素子で検出するものです。 このセンサが使われなかった大きな理由は、出力の経時変化(ドリフトといいます)が大きかったためです。 車が曲がる時の角速度はとても小さい場合が多いのです。ゆっくりと車庫入れや、 ゆるやかなカーブを曲がる時など曲がりきるまでにかなり時間がかかる場合があります。 その非常に小さい角速度を積分して回転角を求めるのですが、積分している間にセンサの出力が変化するため、 誤差が大きくなって実用水準には達しませんでした。同じ原理ですが、光ファイバジャイロを検討したメーカーもありました。 しかし、価格がとても高く、採用できなかったと聞いています。適正な価格で、感度が高く、出力の経時変化が少ないセンサがどうしても必要でした。
 筆者の知る限りでは、現在多くのカーナビゲーションシステムに採用されているセンサは松下電子部品が製造する水晶角速度センサのようです。
原理はこれまで試された角速度センサと同じですが、水晶を使ったもので、感度が25mV/°/秒と非常に高く、出力のドリフトも少ないのです。
筆者の知る限りでは、現在多くのカーナビゲーションシステムに採用されているセンサは松下電子部品が製造する水晶角速度センサのようです。
原理はこれまで試された角速度センサと同じですが、水晶を使ったもので、感度が25mV/°/秒と非常に高く、出力のドリフトも少ないのです。
カーナビゲーションシステムではセンサの出力をGPSから得られた情報で補正して使います。これがハイブリッド航法の基本になります。
高速で直線走行している状態でGPS衛星からの信号が安定に受信できると高い精度の進行方向が得られます。
また、緯度経度の変化から移動量もかなり正確にわかるので車速パルスから得られる距離の補正も行えます。
このような方法でタイヤの磨耗、空気圧の変動などを補正しているので、カーナビゲーションシステムを搭載した場合、
時折GPS受信状態の良い場所で直線走行を行わないと誤差が大きくなる可能性が出てきます。
| << BACK | NEXT >> |
